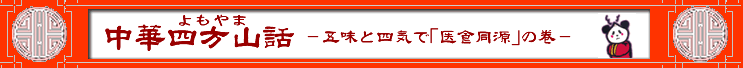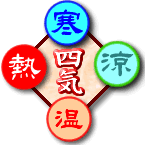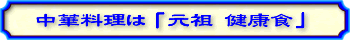
「中華料理は脂っこい」 という先入観をお持ちの方が多いようですが、実際には、植物性の油を使っていますので、決して脂っこいわけではありません。また、その量も、考えるほど多く使っているわけではないのです。
中華料理では、旨みやコクを引き出すために油を 上手く使い、食材の栄養を効率よく吸収させるために活用していますし、使用している食塩の量も少ないので、むしろ、お年寄りや高血圧の方などにもお薦めできるくらいなのです。
中国では、秦の始皇帝以来、不老不死の仙薬を探し続けましたが、それは、やがて、身体に良い食べ物、身体を丈夫にする食べ物、また、その組み合わせという考え方、つまり、「医食同源」という考え方にになって、現代に至っています。
そうした健康と食の追及の中で培われてきた「食のノウハウ」のひとつに、基本となる考え方が「五味」と「四気」があります。
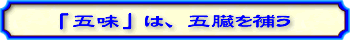
五味とは、文字通り「5つの味」のことです。「五味は五臓を補う」とされています 。
 |
(サン)すっぱい味…。筋肉などを引き締める収斂(しゅうれん)作用があるので、下痢や寝汗などに良い。 |
 |
(ク)苦い味…。消炎作用や固める作用があるので、出血性疾患や下痢に良いとされている。 |
 |
(カン)甘い味…。緩和作用があるので、鎮痛や、トゲ抜きに良いとされる。 |
 |
(シン)辛い味…。発散作用があるので、風などに良く、発刊を促す作用がある。 |
 |
(カン)塩辛い味…。軟化作用があるので、大乗便の通じを良くし、疝気(せんき)などの痛みを治す。 |
このような考え方を基本に組立て、下の組み合わせで料理するのが原則となっています。
|
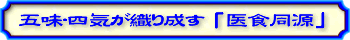
医食同源を志す、中華料理のもうひとつの考え方が「四気」、つまり、寒暖を基本とした考え方です。
食材の持つ性質を熟知し、身体にもたらす効果を知った上で調理することが、もうひとつの秘訣です。
 |
(カン)…身体を冷やす。鎮静、消炎作用がある。のぼせ症や血圧の高い人に良い。 |
 |
(リョウ)…。鎮静、消炎作用がある。のぼせ症の人に良い。寒より弱い。 |
 |
(オン)…。身体を温める。興奮作用がある。冷え性の人に良い。 |
 |
(ネツ)…。身体を温める。興奮作用がある。貧血、冷え性の人に良い。温より強い。 |
下の食物は、身体の調子、病状により、やめた方が良いとされています。
| ホーレン草 |
腎臓、膀胱結石 |
| パセリ |
胃、十二指腸潰瘍、皮膚疾患 |
| 筍 |
気管支炎、咳、痰、腎臓、皮膚疾患 |
| ニンニク |
胃炎、腸炎、眼病 |
| 蝦、蟹、ウニ |
皮膚疾患 |
| スモモ、胡麻 |
下痢 |
|